離婚したいけれど、「いくら費用が必要になるのか」など、お金に関する不安を抱いていないでしょうか。
離婚届の提出に、お金はかかりません。
しかし、離婚すると、新生活に必要な費用などさまざまなお金が必要になると考えられます。
また、夫婦間の話合いで離婚できない場合には、調停や裁判が必要になるため、手続そのものにかかる費用や、弁護士費用が必要になるでしょう。
一方で、離婚すると、場合によっては慰謝料や養育費、財産分与などを受け取れることがあります。
離婚したいと思っているのであれば、前もって離婚にいくらお金が必要になるのか、受け取れるお金はどれくらいなのかについて知っておきましょう。
このコラムでは、離婚にまつわる費用やお金について弁護士が解説します。
離婚に必要な費用
離婚に必要な費用は、次のうちどの方法で離婚するかによって大きく変わります。
- 話合いにより離婚するケース
- 調停や裁判で離婚するケース
それぞれについて説明します。
(1)話合いにより離婚するケース

話合いで離婚する場合には、離婚条件を夫婦で話し合って決め、離婚届を提出すれば離婚が成立します(協議離婚)。
離婚届の提出にお金はかからないため、離婚の手続自体にかかる費用はありません。
ただし、離婚協議書を公正証書として作成する場合には、公正証書を作成する際に手数料がかかります。
(2)調停や裁判で離婚するケース

離婚に向けた話合いがまとまらず、調停や裁判が必要になった場合、次のような費用がかかります。
- 調停や裁判に必要な費用
- (弁護士に依頼する場合)弁護士費用
(2-1)調停に必要な費用
離婚調停にかかる費用は、どういったことを調停で話し合うのかにもよりますが、3,000円程度となることが一般的です。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 収入印紙代 ・夫婦関係調整調停(離婚) ・面会交流調停 ・婚姻費用の分担請求調停 | (※1) 1,200円 1,200円(子ども一人につき) 1,200円 |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 発行費用450円(郵送で取得する場合には別途郵送費などが必要) |
| 切手代 | 1,000円程度(※2) |
| その他必要な資料の取得費用 | 資料によって異なる |
※2 申し立てる家庭裁判所によって異なり、家庭裁判所のホームページに掲載されていることもあります。詳しくは、事前に家庭裁判所にご確認ください。
(2-2)裁判に必要な費用
離婚裁判にかかる費用は、離婚だけを求める場合であれば2万円程度となることが一般的です。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 離婚のみの場合 | 13,000円 |
| 離婚と合わせて財産分与などを求める場合 | 各1,200円を加算する。 例)離婚、財産分与、子3人の養育費を請求 13,000円+1,200円(財産分与)+1,200×子3人=17,800円 |
| 離婚請求と合わせて慰謝料を請求する場合 | 13,000円と慰謝料請求に対する印紙代を比べて、多額の方に財産分与などの手数料を加算 例)離婚、財産分与、子3人の養育費と、慰謝料300万円を請求 慰謝料300万円の印紙代は2万円で、離婚のみを求める13,000円よりも多額なので、2万円+1,200円(財産分与)+1,200円×子3人=24,800円 |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 発行費用450円(郵送で取得する場合には別途郵送費などが必要) |
| 切手代 | 5,000~6,000円程度(家庭裁判所によって異なる) |
| その他必要な資料についての取得費用 | 資料によって異なる |

このほかに、裁判に鑑定や証人が必要となった場合には、鑑定費用や証人の日当などが必要となることがあります。
(2-3)弁護士費用
弁護士に依頼すると、調停や裁判をするためにかかる費用とは別に弁護士費用も必要になります。
弁護士費用の内訳は大きく分けて、着手金、報酬金、実費などです。
離婚に関する弁護士費用の場合、離婚だけを請求するのか、離婚とともに親権や慰謝料も請求するのか、などによって着手金や報酬金が異なります(内容が複雑になればなるほど金額は高額となります)。
弁護士費用は法律事務所ごとに異なるため、不明点はしっかりと確認しましょう。
たとえば、一般的な弁護士費用は次のとおりです。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 相談料 | 1時間など一定時間は初回無料~1時間1万円程度 |
| 着手金(依頼時に発生する費用) | 20万~40万円程度(※1) |
| 報酬金(※3)(成功時に発生) ・基本報酬金 ・成功報酬金 離婚成立 親権獲得 慰謝料や財産分与など | 20万~40万円 20万~50万円 10万~40万円 合意金額又は回収金額の10~20% |
| 日当(調停・裁判への出頭費用) | 0~5万円程度(※2) |
| 実費 | 印紙代、切手代、交通費など |
※2 日当がかからない法律事務所もあります。そのような場合、一般的に、着手金が少し高めになることが多いようです。また、裁判所に出廷せず、事務所で電話やオンライン会議で裁判所の期日に対応することがあり、別途その費用について取り決めのある事務所もあります。
※3 報酬金も事務所ごとに異なり、慰謝料や財産分与の額によって、成功報酬のパーセンテージが異なる場合もあります。
(3)どちらのケースであっても必要となる費用
離婚の際には、引越し費用や転居先の家具家電の購入費用など、新生活のためのお金も必要です。
たとえば、引越し費用や家具家電一式の購入費用の相場は次のとおりです。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 引越し費用 | 数万~30万円程度 |
| 家具家電一式の購入費用 | 20万~100万円程度 |
離婚の際に検討すべき「お金」のこと
離婚の際には、財産分与や養育費などについての検討も必要です。
具体的には、主に次の5つです。
- 別居中の生活費(婚姻費用)
- 財産分与
- 養育費
- 離婚慰謝料
- 年金分割
それぞれについて説明します。
(1)別居中の生活費(婚姻費用)
婚姻費用とは、家族が通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことをいいます。
具体的には、居住費や生活費、未成熟子(※)の生活費や学費といった費用です。
未成熟子とは、未成年と同じ意味ではなく、まだ社会的経済的に自立して生活できない子どものことです。
たとえば、18歳以上であっても、学生であれば未成熟子とされる可能性があります。

別居中であるなど、夫婦関係が破綻していたとしても、離婚までは、原則として収入の高い夫(妻)が低い妻(夫)に対して生活費(婚姻費用)を払う義務があります。また、同居中であっても、婚姻費用を請求できる場合があります。
(2)財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に清算し分配する制度のことです(民法第768条)。
夫婦の共同名義で購入した不動産や、夫婦の共同生活に必要な家具や家財だけでなく、夫婦どちらかの名義となっている預貯金や車、有価証券、退職金であっても、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象になりえます。
(3)養育費
「養育費」とは、衣食住の費用、教育費、医療費などの未成熟子の養育に必要な費用のことをいい、定期的、継続的に支払っていくものです。
婚姻費用と似ていますが、婚姻費用は結婚している間のみ支払う費用で、配偶者の生活費も含まれます。
一方、養育費は子どもの監護に必要な費用であるため、元配偶者の生活費は含まれず、離婚後に支払われるものです。

離婚して子どもと離れて暮らすことになっても、親であることに変わりはありません。
したがって、「生活が苦しい」という理由で養育費の支払義務を免れることはなく、生活水準を落としてでも支払う義務があります。
(4)離婚慰謝料
「離婚慰謝料」とは、離婚によって生じた精神的苦痛を金銭に換算したもので、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償の一つです。
たとえば、配偶者の不貞行為、DV、ハラスメント行為が原因で離婚する場合、その原因を作った配偶者に、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
(5)年金分割
「年金分割」とは、離婚後2年以内に、婚姻期間に対応する厚生年金(※)の保険料納付記録の最大2分の1を分割し、分割を受けた方が、分割された記録に基づいて、将来、厚生年金を受給することができる制度のことです。
※2015年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されています。
なお、保険料納付記録を分割するものであり、元配偶者の年金額の最大半分をもらえるという意味ではないため、ご注意ください。
熟年離婚の場合、年金が離婚後の生活の原資となることが多いはずです。
離婚前であっても、年金分割の話合いに必要な情報は「年金分割のための情報通知書」を入手すればわかるため、加入している年金団体に請求するとよいでしょう。
離婚後の生活に不安がある場合
離婚後の生活に、経済的な不安がある方も多いはずです。
離婚後の生活の収支を見積もり、経済的に自立した生活を送っていけるか、公的支援を受けないといけないかなどについても検討しておきましょう。
また、自分が受けられそうな公的支援などの制度について、あらかじめリサーチしておきましょう。
【まとめ】離婚の方法によって必要な費用は異なる|もらえるお金も把握しておこう
離婚には、話合いによって離婚する方法と、調停や裁判で離婚する方法があります。
話合いで離婚する場合、離婚条件を夫婦で話し合って決め、離婚届を提出すれば離婚が成立します(協議離婚)。
離婚届の提出にお金はかからないため、離婚自体にかかる費用は基本的にありません。
調停や裁判で離婚する場合、調停や裁判に必要な費用だけでなく、弁護士に依頼するのであれば弁護士費用も必要になるでしょう。
また、離婚の際には、引越し費用や転居先の家具家電の購入費用など、新生活のためのお金も必要です。
一方、財産分与や離婚慰謝料など、もらえる可能性のあるお金もあるため、離婚条件について事前にしっかりと考えておくことが大切です。
事前に離婚後の生活の収支を見積もり、経済的に自立した生活を送っていけるか、公的支援を受ける必要があるかについて検討しておきましょう。
離婚条件などでお悩みの方は、離婚問題を取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。



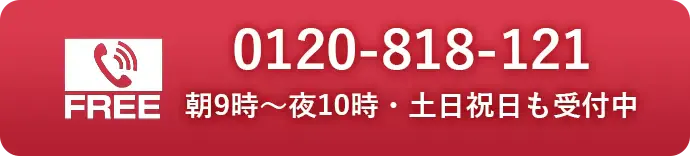
どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。